受粉
昨今では農業ロボットの開発も進んでおり、様々な工程で新しい技術が活かされています。そこで今回は、花や実を作るための工程のひとつである「受粉」について、自動で行ってくれるシステムは存在するのか見ていきましょう。
受粉ロボット「XV2」

(https://harvestx.jp/)
受粉ロボットとして開発されているものとして代表的なのは、HarvestX株式会社による新型自動栽培ロボット「XV2」。これは主にいちごの受粉を行うために研究したとのことで、磁気誘導方式による自動走行機能でのロボット受粉が可能なだけでなく、収穫にも対応しています。
「XV2」の性能や価格は?
XV2の性能や価格については、2022年5月現在は記載がありませんでした。まだ研究段階の可能性もありますので、詳しくは開発元にお問い合わせください。
- XV2(自律走行・収穫トレイの交換機能等) 要問い合わせ
「XV2」の導入メリット
受粉は通常人の手でひとつひとつ丁寧に行う必要がある上、花が散ってしまうと作業が難しいため、人件費や作業時間の確保など様々な課題が生まれやすいですよね。
しかし、XV2は自動走行しながら受粉作業を自力で完了することが可能なので、人員を他の作業に割けるメリットが期待できます。特に植物工場での需要が見込まれており、今後もより一層の製品強化に努めていくそうです。
「HarvestX」ってどんな会社?
HarvestXは、いちごの受粉と収穫を行うためのシステムをはじめ、農業ロボットの開発を中心に研究している会社。特に植物工場における自動農業実現を目指し、ソフトウェアソリューションを含めた製品の提供を行っています。
全自動受粉や検出アルゴリズム、ロボットコントロールなどのテクノロジーを活かした製品たちは、いずれも次世代の農業への大きな貢献が期待されるでしょう。
| 会社名 | HarvestX株式会社 |
|---|---|
| 問い合わせTEL | 記載なし(メールにて対応) |
| 本社所在地 | 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学南研究棟アントレプレナーラボ 253 |
| URL | https://harvestx.jp/ |
受粉農業ロボット開発事例(Arugga社)
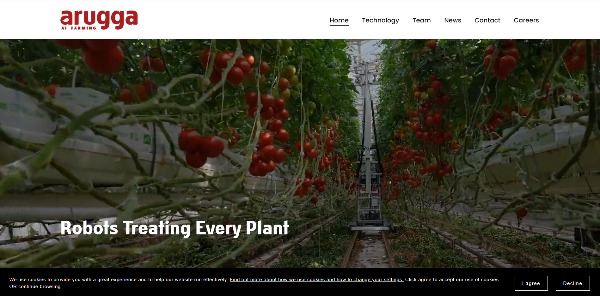
(https://www.arugga.com/)
研究段階(2020年末発売との記載がありますが、現時点で続報がないようです)の受粉ロボットとしては「TRATA」が挙げられます。これはイスラエルを拠点とする農業スタートアップ企業「Arugga社」にて研究されているもので、ベルギー、カナダの生産者チームとも協力しながら実用化に向けて取り組んでいるとのこと。
「TRATA」の性能や
想定価格は?
価格については記載がありませんが、基本的にはトマトをはじめとした温室栽培の効率化を想定した性能となっており、マルハナバチの受粉の受粉を再現したシステムであるのが特徴です。
マルハナバチの受粉には特定の環境条件が必要とされていますが、TRATAは農薬の影響等の課題も含め、既に問題を解決しています。2020年当時の研究段階では全体の約97%の花を発見し、受粉することができたそうです。
- TRATA 価格の記載なし
「Arugga」ってどんな会社?
イスラエルを拠点とするArugga社は、日本ではあまり馴染みがない会社かもしれません。しかし、少数精鋭で温室内の植物を監視し扱うことが可能な自律型ロボットを提供するなど、新しいテクノロジーを活かした様々な研究が注目されています。
スマート農業によって世界的に問題視されている農家の労働力不足を助け、より健康な地球環境の実現に貢献したいと考えているそうです。
| 会社名 | Arugga社 |
|---|---|
| 問い合わせTEL | 不明 |
| 本社所在地 | 不明 |
| URL | https://www.arugga.com/ |
| 展示会出展実績 | 要問い合わせ |
まとめ
受粉は農業の工程の中でも非常に手間がかかる作業なので、ロボットによって効率化できれば助けられる農家は多いのではないでしょうか。今回ご紹介したようにいまだ研究段階の部分も大きい分野ではありますが、農業ロボットはもちろん、中にはドローンを用いた受粉等も検討されているようですから、今後の更なる発展を楽しみに待ちましょう。
